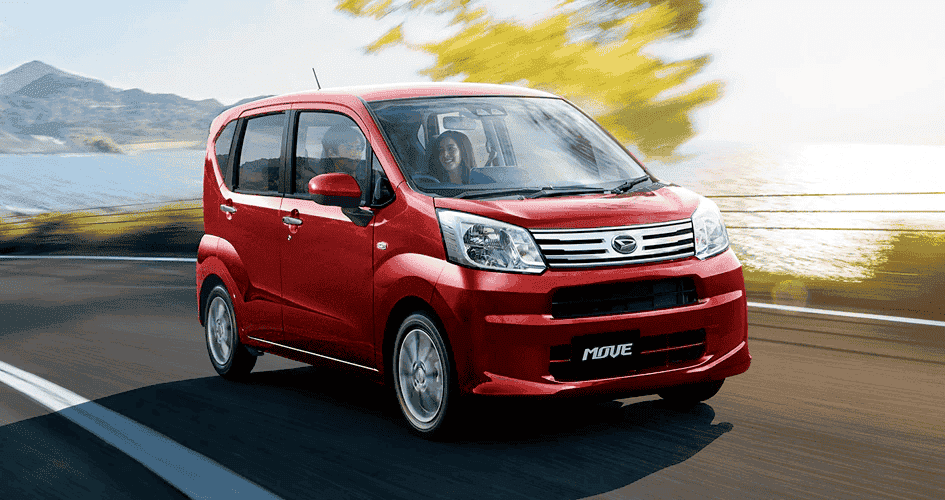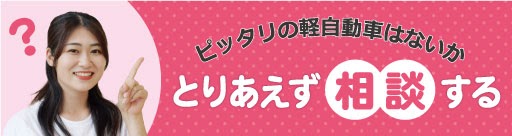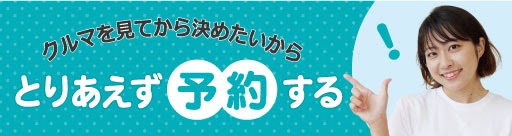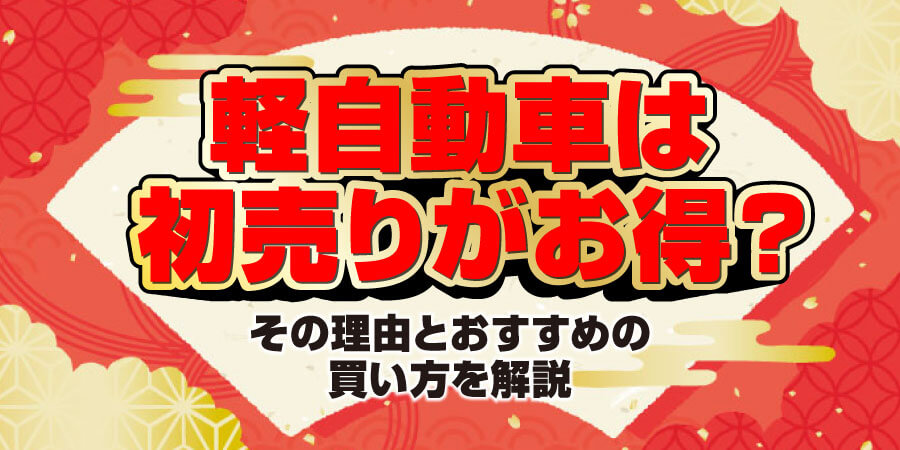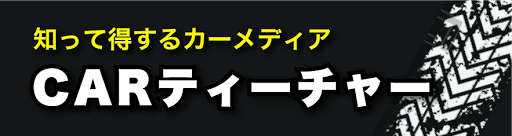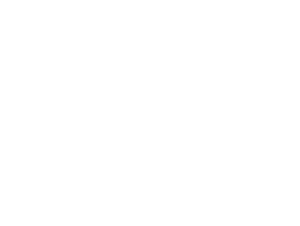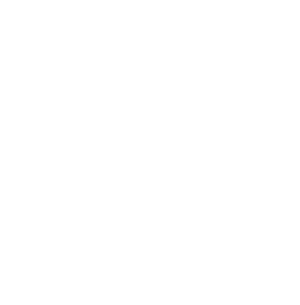軽自動車といえば、ひと昔前まではセカンドカーとしてのイメージが強かったのですが、燃費や性能の向上に伴い、今ではメインカーとして考えているユーザーが多くなっています。
車両価格だけでなく維持費も抑えられるため、コスパを重視する方にもおすすめの車と言えるでしょう。
では、そんなコスパのよい軽自動車は一体どれくらい乗り続けられるのでしょうか?
今回の記事は、軽自動車の寿命を解説しながら、日々のメンテナンスや買い替えのタイミングなどを詳しく紹介いたします。
目次
軽自動車とは

軽自動車とは、日本独自の規格を持つ小型の自動車のことです。
軽自動車として認められるためには、法律で定められた規格を満たす必要があります。
普通自動車の規格と比較し確認してみましょう。
| 軽自動車規格 | 普通車規格 | |
|---|---|---|
| 全長 | 3.40m以下 | 3.40mを超えるもの |
| 全幅 | 1.48m以下 | 1.48mを超えるもの |
| 全高 | 2.00m以下 | 2.00mを超えるもの |
| 排気量 | 660cc以下 | 660ccを超えるもの |
| 定員 | 4名以下 | 4名を超えるもの |
| 貨物積載量 | 350kg以下 | 350kgを超えるもの |
つまり、軽自動車の規格を超える自動車は、すべて「普通自動車」に分類されます。
軽自動車は、「サイズ・排気量・定員」などが厳密に定められており、普通自動車に比べて税金や保険が安く、燃費が良いという大きなメリットがあります。
また、小回りの利くサイズの取り回しの良さや、多様なラインナップといった独自の魅力から、日本の道路環境や消費者のニーズに非常に合致した実用的な車と言えるでしょう。

軽自動車の寿命

一般的な国産乗用車(普通自動車が主流)に対して、以前は「10年または10万km」が目安と認識されていました。
軽自動車は限られた排気量の中で普通車と同じ速度で走行するため、エンジンにかかる負荷が相対的に大きく、部品の耐久性から「普通車よりも寿命が短い」と言われることもありました。
しかし近年の技術革新により、軽自動車の耐久性が向上し、現在では適切なメンテナンスを行えば10年より長く、普通自動車と遜色ないくらい乗り続けることが可能になります。
実際どれくらい乗り続けられているか、近年の平均使用年数の推移を見てみましょう。
日本国内の統計データ
軽自動車検査協会の「軽自動車の平均車齢・平均使用年数」から、乗用軽自動車の平均使用年数(新車届出から廃車までの期間)を確認すると、平均使用年数は年々増加傾向にあるのがわかります。
2024年の軽自動車(自家用車)の平均使用年数は16.21年。
目安と言われていた10年より、6年も延びています。
対して、普通車の平均使用年数は、2024年3月末時点で13.32年。(一般財団法人 自動車検査登録情報協会調べ)
驚くことに、普通車よりも長い年数使用されているのです。
年数と走行距離の目安
「普通車より寿命が短い」と言われていた理由に、エンジンの負荷や部品の耐久性を例に挙げました。
技術革新により軽自動車の耐久性は大幅に向上したものの、一般的には「普通車の7~8割」と言われています。
現在の普通車の寿命目安が15年/15万km以上なので、その8割で算出すると「12年/12万km」が軽自動車の寿命目安です。
しかし、乗り方やメンテナンス頻度によって、前項でご紹介した様に16年近く乗ることも可能になります。
軽自動車の寿命を延ばすためのメンテナンス

ここで、長く乗り続ける為のメンテナンスのポイントを紹介します。
定期的なオイル交換の重要性
定期的なオイル交換はエンジンの寿命に直結します。
エンジンオイルは、単にエンジンを潤滑するだけでなく、多岐にわたる重要な役割を担っていますが、使用するうちに劣化していきます。
寿命を延ばしエンジン性能を最大限に引き出すため、適切な種類と粘度のオイルを選び、3,000~5,000kmごと、または半年ごとを目安に交換することが大切です。
タイヤとブレーキの維持管理
タイヤとブレーキは、どちらも消耗品でありながら、車の安全性と性能の根幹を支える重要な部品です。
タイヤの適正空気圧は、転がり抵抗を最小限に抑えエンジンの負担を減らします。
月に一度はガソリンスタンドやカー用品店、ディーラーなどで空気圧やひび割れ、異常な膨らみがないかをチェックし、タイヤの溝の深さが使用限界(1.6mm)に達する前に交換しましょう。
さらに、ブレーキシステムの適切な維持は、万が一の事故を防ぐだけでなく、他の部品の寿命にも影響します。
ブレーキを踏んだ時に摩擦を起こすブレーキパッドは、摩耗するとブレーキの効きが悪くなります。
限界を超えて摩耗すると金属同士が擦れてブレーキディスク(ローター)まで損傷し、交換費用が高額になる可能性があります。
定期点検時にブレーキパッドの残量をチェックし、ブレーキフルード(ブレーキに伝える油圧の液体)、ブレーキディスク(ブレーキパッドが挟み込む円盤状の部品)は、2年ごと(車検ごと)の交換を検討しましょう。
洗車と車体保護管理の利点
定期的な洗車も、異臭やタイヤの状態など異変に気づくきっかけになるので、月に1回程度でも行うと良いでしょう。
直射日光や雨風にさらされ続けるより、屋根付きの駐車場などに保管されている方が、ボディや部品の劣化が遅くなります。
また、エンジンが十分に温まらない短距離走行の繰り返しはエンジンに負担がかかりやすくなるため、最低でも月2回程度は10km以上の走行をおすすめします。

軽自動車の寿命を判断するポイント

軽自動車の寿命を判断する際、明確な「この状態になったら終わり」という一線はありませんが、いくつかのサインを紹介します。
様々なサインや状況を総合的に見て判断しましょう。
◆エンジンの状態チェック
「ガラガラ」「カンカン」「ゴロゴロ」といった大きな異音がする場合、エンジン内部のベアリング、ピストン、バルブなど、主要な金属部品の摩耗や損傷が考えられます。
特に、エンジン回転数に応じて音の大きさや種類が変わる場合は重症のサインです。
◆タイミングベルトの寿命
タイミングベルトは、エンジンの動きを正確に同期させる役割を担っています。
ゴム製品であるタイミングベルトは消耗品であり、経年劣化します。
ユーザーが目視で劣化状態を確認することは非常に困難となるため、メーカーが指定する交換時期や、点検で整備士から交換を勧められた場合は、安全のために早めの交換を検討しましょう。
※以前はゴム製であったため、10万kmで交換が目安とされたタイミングベルトですが、近年は金属製のタイミングチェーンに代わり、20万km程度まで保つ車種が増えてきました。
◆バッテリーの劣化サイン
バッテリーは消耗品であり、ある日突然寿命を迎えることも少なくありません。
エンジン始動時に「キュルキュル」というセルモーターの音が弱々しくなったり、回転が遅くなったりするのは、バッテリーの蓄電能力が低下している代表的なサインです。
一般的に、車のバッテリーの寿命は2年~3年が目安とされています。
買い替えを検討すべき時期

昔に比べて軽自動車の耐久性は格段に向上しており、適切なメンテナンスを行えば一般的な目安よりも長く乗り続けることが十分可能ですが、安全面や経済面での負担が増えてきます。
寿命サインがなくても買い替えを検討すべき時期をご紹介しましょう。
◆走行距離に基づく判断
走行距離「10万km~15万km」が一つの目安とされています。
「10万km~15万km」という走行距離は、多くの部品の寿命が集中する時期であり、その結果として修理費用が増加し、経済的な負担が大きくなるタイミングであるため、車の寿命や買い替えの目安としてよく挙げられます。
◆車検・修理を考慮したタイミング
10万kmを超えた辺りから、消耗品の交換だけでなく、大きな修理が必要になるケースが増え、修理費用が高額になることがあります。
車検や修理費用を確認し、費用を払ってでも今の車に乗り続けるのかを考えてみましょう。
◆リセールバリューの低下
一般的に、年式が古くなり走行距離が長くなるほど、下取り価格は大幅に下がります。
例えば、10年を超えた車は、新車価格の10%以下まで価値が下がる傾向にあり、車種によっては、ほとんど価格がつかない(残価率が数%)場合も珍しくありません。
また、モデルチェンジや生産終了する場合も下取りや買取価格の相場が、大きく下がるので注意が必要です。
売却価格を把握し、下取り価格がつくうちに買い替えるという考え方もあります。
◆燃費の悪化とその影響
燃費悪化は、車のコンディションを示す重要なサインの一つです。
エンジンの劣化や部品の摩耗により、燃費性能が新車時より悪化することがあります。
以前は1リットルあたり15km走っていたのに、最近は同じ走り方で12kmや10kmしか走らなくなった、など、3km/L以上の低下が続くようであれば、検討のサインです。
特に給油頻度が明らかに増えたと感じる場合は、買い替えの検討時期として適切かもしれません。
◆税金の負担が増すタイミング
軽自動車は、新車登録から13年が経過すると、自動車税・重量税が増額されます。
自動車税は「グリーン化税制(重課)」と呼ばれ、新車登録から13年が経過した翌年度から環境性能の良い新しい車への買い替えを促し全体の環境負荷を低減することを目的として、概ね20%増額されます。
また、自動車重量税は13年経過した車検時から約24%増、18年経過した車検時からは、さらに10%上乗せした約33%増の2段階で課税されます。
| 経過年数 | 自動車税(年額) | 自動車重量税 (車検ごと2年分) |
|---|---|---|
| ~12年 | 10,800円 | 6,600円 |
| 13年~ | 約20%増 (12,900円) | 約24%増 (8,200円) |
| 18年~ | ― | 約33%増 (8,800円) |
※自動車重量税は車検時に支払うため、新車購入時は初回3年分、以降は2年分を支払います。
これらの増税は、車を長く保有する際の維持費に大きく影響するため、ご自身の車の初度登録年月を車検証などで確認し、いつから増税の対象になるかを把握しておきましょう。
軽自動車を手放す際のポイント
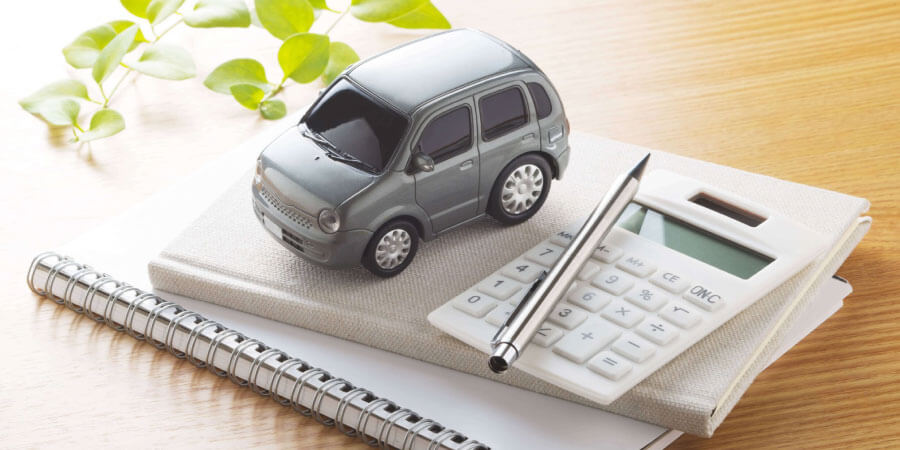
ここで、愛車を手放す方法をご紹介します。
車を手放す方法としては、大きく分けて「売却」と「廃車」の2つの方法があり、それぞれ具体的なステップが異なります。
ご自身の車の状態や、今後どうしたいかによって最適な方法を選びましょう。
車を売却する(まだ価値がある場合)
まだ走行可能で、ある程度の価値が見込める車の場合は、売却が一般的です。
◆下取り(新車・中古車販売店に売る)
新しい車の車種や購入条件を販売店と交渉後、現在の車の「下取り査定」を依頼します。
走行距離、年式、グレード、車の状態(内外装、修復歴の有無など)によって査定額が決まります。
新車の購入と同時に手続きが完結するため手間が少ないですが、買取専門店に比べて、査定額が低くなる可能性があります。
必要書類の準備・提出
・車検証・自賠責保険証明書・自動車税納税証明書(直近のもの)
・印鑑登録証明書(発行3ヶ月以内)・実印・リサイクル券・運転免許証(本人確認のため)
◆買取(中古車買取専門店に売る)
複数の買取専門店に査定を依頼後、実際に車を見てもらい査定額の提示を受けます。
提示された価格や条件に納得できれば契約となり、車を引き渡した後、買取金額が指定口座に振り込まれます。
下取りよりも高値がつく可能性がありますが、新車購入とは別に手続きとなるため、手間がかかり、乗り換えのタイミングがずれる場合があります。
必要書類の準備・提出
・車検証・自賠責保険証明書・自動車税納税証明書(直近のもの)
・印鑑登録証明書(発行3ヶ月以内)・実印・リサイクル券・運転免許証(本人確認のため)
車を廃車にする(価値が見込めない場合)
走行不能な車、修理費用が高額すぎる車、年式が非常に古い車など、売却価値がほとんどない、またはマイナスになる車の場合は廃車となります。
◆廃車業者への連絡
廃車手続きを代行してくれる専門業者(廃車買取業者、解体業者など)に連絡し、車を引き渡します。
※費用がかかる場合と、車種や状態によって買い取ってもらえる場合があります。
不要になった車を確実に処分でき、自動車税などの課税が止まりますが、手続き費用がかかる場合があるので注意が必要です。
必要書類の準備・提出
・車検証・自賠責保険証明書・自動車税納税証明書(直近のもの)
・印鑑登録証明書(発行3ヶ月以内)・実印・リサイクル券・運転免許証(本人確認のため)
◆一時抹消登録または永久抹消登録
一時的に登録を解除するのか二度と乗らず登録を解除するのか、確認しましょう。
通常、廃車業者に依頼すれば、これらの手続きも代行してくれます。
【一時抹消登録】再び車に乗る可能性がある場合に、一時的に登録を解除する方法。自動車税の課税が止まる。
【永久抹消登録】車を完全に解体し、二度と乗らない場合に登録を解除する方法。自動車税・重量税の課税が止まる。
軽自動車を手放す際の注意点
どんな車でも、まずは「下取り」と「買取」の両方で査定を依頼することをおすすめします。
思わぬ価値がつくこともありますし、売却価値がなくても廃車費用の見積もりと比較できます。
また、買取・下取りは、業者によって査定額が大きく異なりますので、必ず複数社に見積もりを依頼し、比較検討しましょう。
売却・廃車後は、きちんと名義変更が完了したか、あるいは抹消登録されたかは、思わぬトラブルを避けるためにも必ず確認しましょう。
廃車手続きを代行してくれる専門業者の選び方
残念ながら悪質な業者も存在するため、信頼できる業者を選ぶことが非常に重要です。
許認可がしっかりしていて、費用が明瞭、そして丁寧な対応をしてくれる業者を選びましょう。
複数の業者から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。
◆許認可・登録の確認
許認可・登録を確認します。
下記許認可情報は、業者のホームページに掲載されていることが多いですが、掲載がなければ直接問い合わせて確認します。
これらの許可を持たない業者は、不法投棄など不適切な処理を行う可能性があり危険です。
| 引取業者登録 | 使用済み自動車の引き取りを行うための登録。 |
| フロン類回収業者登録 | エアコンのフロンガスを適正に回収するための登録。 |
| 解体業者許可 | 車の解体を行うための許可。 |
| 破砕業者許可 | 解体後の車をさらに細かく破砕し、リサイクルするための許可。 |
◆費用の明瞭さ
「廃車費用は無料!」と謳っていても、実際にはレッカー代、書類手続き代行手数料、リサイクル料金(返還されるものと混同しない)、解体費用などが別途発生する場合があります。
必ず総額でいくらかかるのか、何が含まれていて何が含まれていないのかを明確に提示してもらいましょう。
自動車税、自動車重量税、自賠責保険料の還付金がある場合は、その金額や返還時期について、明確に説明してくれるかを確認しましょう。
◆実績と評判
多くの廃車実績がある業者は、手続きにも慣れており、スムーズな対応が期待できます。
大手の全国展開している業者は安心感がありますが、地元密着の業者はきめ細やかな対応が期待できる場合があります。
インターネットの口コミサイトやSNSなどで、実際に利用した人の評判を調べてみるのも手段の一つです。
◆契約書の確認
契約書の内容を必ず隅々まで確認し、不明な点があれば質問して解消してからサインしましょう。
特に、費用や還付金に関する項目は念入りに確認が必要です。
軽自動車の市場動向

最後に軽自動車の人気車種をご紹介します。
新車・中古車問わず軽自動車市場は非常に活発で、多様なニーズに応える様々なタイプが揃っています。
現在最も人気があるのは、やはりホンダ N-BOX を筆頭とするスーパーハイトワゴン。
次いで、SUVタイプが大きく人気を伸ばしています。
1. スーパーハイトワゴン(圧倒的な人気)
全高が高く、広々とした室内空間が最大の魅力。
スライドドアを装備しているモデルが多く、子育て世代や荷物の多い方に絶大な人気を誇ります。
・ホンダ N-BOX・スズキ スペーシア・ダイハツ タント・日産 ルークス など
合わせて読みたい
2025年4月、ホンダからN-BOXの一部改良が発表されました。
装備やカラーバリエーションが追加された新しいN-BOX。
そのパワーアップした魅力に迫ります。 スズキの軽スーパーハイトワゴン スペーシア。
インテリアデザインや収納、シートアレンジも魅力的で、車内空間の完成度には定評があります。
今回は、そんなスペーシアの内装の特徴に触れてまいります。 ダイハツの人気車種タント。
2022年のマイナーチェンジ、そして10月に追加されたタントファンクロスの登場でますます魅力がアップしています。
マイナーチェンジの内容や新モデルについて詳しくご紹介します。 日産自動車は2023年4月17日に人気のスーパーハイトワゴン「ルークス」をマイナーチェンジし、6月下旬に発売することを発表しました。
今回の記事では、マイナーチェンジによって内外装の変更だけでなく安全装備も強化され、さらにパワーアップしたルークスの魅力をご紹介します。

【2025年4月】ホンダ N-BOXが一部改良!価格や装備はどう変わった?

スズキ スペーシアの内装の特徴は?モデル別の違いやおすすめポイントを紹介

タントがマイナーチェンジ!新型モデル紹介と注意ポイント

日産ルークスがマイナーチェンジ!内装外装の魅力をご紹介
2. SUVタイプ(人気急上昇中)
SUVらしい力強いデザインと、最低地上高の高さによる取り回しの良さが魅力の車です。
アウトドアやレジャーを楽しむ層から支持されています。
・スズキ ハスラー・ダイハツ タフト・三菱 デリカミニ
合わせて読みたい
スズキのハスラーが一部仕様変更!
ハスラータフワイルドの変更点や魅力をお伝えしてまいります。
ますますレベルアップしたハスラーの新仕様車をご覧ください。 ダイハツのタフトが一部仕様変更!
仕様変更の内容をご紹介しつつ、タフトの魅力をあらためてご紹介します。
ベース車と特別仕様車の違いにもご注目ください。 三菱自動車の軽スーパーハイトワゴン「デリカミニ」。
設定されている4つのグレードを、価格や燃費、装備などをもとに比較していきます。
デリカミニの特徴や魅力をたっぷりとご覧ください。

【2024年】人気の軽SUVスズキハスラー一部仕様変更でタフワイルドが仲間入り!変更点と魅力をご紹介

【2024】ダイハツタフトが一部仕様変更で安全性が向上!特別仕様車の内装や違いも説明

三菱デリカミニの全グレードを比較&おすすめポイントをご紹介!価格や装備はどう違う?
3. ハイトワゴン(定番の安定人気)
スーパーハイトワゴンよりは全高が低いものの、十分な室内空間と使い勝手の良さを持ち、運転のしやすさも魅力です。
・スズキ ワゴンR・ダイハツ ムーヴ
4. セダンタイプ(経済性重視)
全高が低く、コンパクトで軽量。
圧倒的な燃費性能と手頃な価格が魅力です。
・スズキ アルト・ダイハツ ミライース
軽自動車の寿命について まとめ

ここまで、軽自動車の寿命を解説しながら、日々のメンテナンスや買い替えのタイミングなど紹介してきました。
今後の技術発展に伴って、軽自動車の寿命は今後も緩やかに延びていくと考えられます。
技術の進化によっては、寿命の判断基準が「物理的な寿命」ではなく、「最新技術への追従」や「経済性・安全基準」といった側面になるかもしれません。
そうなれば、自ずと買い替え意識も変化するでしょう。
届出済軽未使用車専門店レディバグでは、さまざまな軽自動車を検索・ご覧いただける他、経験豊富なカーライフアドバイザーが車種ごとの情報や車の選び方など、ご希望に合わせてご案内いたします。
軽自動車についてのご相談なら、レディバグへ気軽にお問い合わせください。


埼玉県の三郷市・越谷市・春日部市に店舗を構える軽自動車専門店、レディバグ。
私たちは低価格で高品質な届出済未使用車(新古車)を提案し、トータルサポートを通じて安心・安全なカーライフをお約束します。

 0120-782-588
0120-782-588